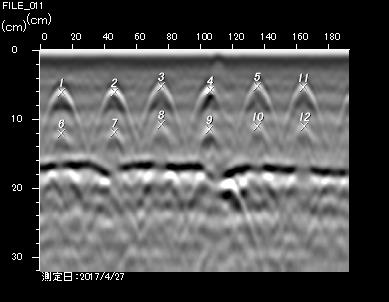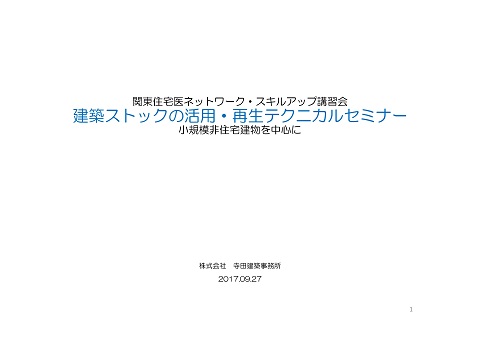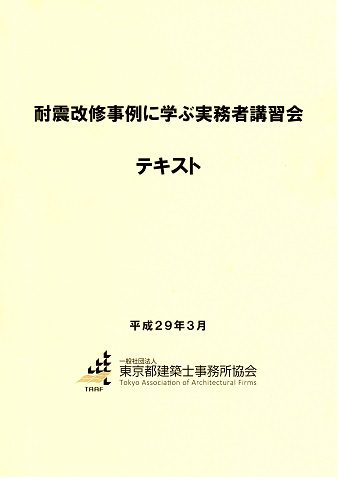病理医は、病理診断をする医師で基本的な仕事として「病理解剖(部検)」「組織診断(生研及び手術材料)」「細胞診断」があるそうです。
以下「日本病理学会」サイトからの引用です。
「病理解剖は病院で不幸にして亡くなられた患者さんの死因、病態解析、治療効果などを検証し、今後の医療に生かすことを目的に行います。
組織診断は内視鏡医がみつけた病変部から採取(生検といいます)した、小さい組織片を顕微鏡でみて診断したり、手術して切除された検体から臨床診断を確認したり、どの程度病気が進展しているかなどを検証する作業を行うことです。手術中の短時間に病理診断を下して、手術方針を決めるのに役立つ「術中迅速診断」も病理医の重要な業務です。
細胞診断は婦人科医が子宮粘膜表面から細胞を採取したり、外科医が乳腺など体表に近い病変部から注射器で針を刺して細胞を採取して検査することです。細胞診断は細胞検査士という日本臨床細胞学会が認定した資格をもつ専門技師と共同で診断します。病理医は病理診断に迷うこともあります。その時はこれが自分や自分の家族だったらどう診断するかと思いをめぐらせることで、答えが自ずと見えてくることがあります。もちろん、難解で自分の手に負えないと思えば臓器別専門の病理医に標本を送ってアドバイスを請うことも少なくありません。これをコンサルテーションシステムとよび、日本病理学会の重要な業務の一つとなっています。
この3大業務以外にも臨床各科と合同で解剖例や手術例についてカンファレンスを行ったり、院内医療安全検討会のメンバーとなって病理の立場から意見を述べたりすることもあります。最近は主治医の立ち会いのもとで、病理医が患者さんに写真や図を示しながら病理診断の説明を行う病理外来を実施する施設も見られるようになってきました。また、蓄積された病理データを使って臨床研究も積極的に行っています。」
「病理医のつよみは、何と言っても、『病気の総合的判断が可能な医師である』点です。その理由として、全科の検体を扱っていること、剖検による全身の病態診断に慣れていること、病理総論的見方を訓練されているために全身の臓器に共通した病変の概念を理解していることなどがあげられます。言い換えれば、病気を正常からの逸脱の度合いという見方からとらえ、病気の本質的な部分を深く考えている医師が病理医と言えるでしょう。」
しかしその病理医も、まだ全国に2,232名(平成26年9 月現在)しか病理専門医がおらず、決して十分とは言えないそうです。
病理医は患者と直接対面する機会が少ないからでしょうか、以前はそういう専門医がいることを知りませんでした。私が大学病院で2回の整形外科の手術を受けたときも、徹底的な入院前検査、手術前検査を受けました。しかし教授回診、担当医師のみならず多くの整形外科チームの医師や内科医などの他、麻酔医師とは直接面談しましたが、病理医と接する機会はありませんでした。
病理医という専門医がいることを知ったのは、2006年に出版された海堂尊の「チームバチスタの栄光」という小説・映画からでした。
その中に鳴海涼基礎病理学教室助教授という病理医が出場します。桐生の義弟で考えも桐生と似通る部分もあり、かつて桐生とアメリカで外科医をしていたが、病理に興味を移し病理医に転進した人です。「ダブル・ステイン法」という術中診断法を確立させ、「診断と治療は分けるべき」という考えから、会議には参加しないが病理医ながらも桐生と切除範囲を決める形で手術に参加している人物として描かれています。
日本の建築界にも「建築病理学」の確立が必要だと固く信じている私としては病理学の手法は勉強になります。










 鉄骨の調査の為に天井点検口を設置した。
鉄骨の調査の為に天井点検口を設置した。








 【鋼材判別機 サムスチールチェッカー D-200型 立花エレテック】
【鋼材判別機 サムスチールチェッカー D-200型 立花エレテック】










 今日は、昼から日経アーキテクチュア 専門セミナー「改修で失敗しない素材&技術講義」と題した青木茂建築工房の話を聞いてきました。
今日は、昼から日経アーキテクチュア 専門セミナー「改修で失敗しない素材&技術講義」と題した青木茂建築工房の話を聞いてきました。